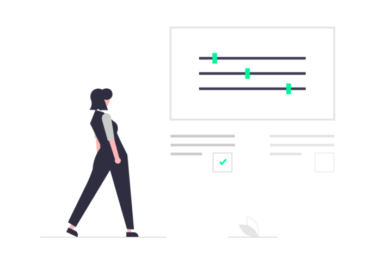変形労働時間制の一つであるフレックスタイム制を導入する場合には、就業規則の規定だけでなく労使協定の締結も必要です。制度導入のために必要な要件など基本事項を整理しました。
フレックスタイム制の適用のために必要な二つの要件
制度導入には、
❷労使協定の締結
の両方が必須要件です。
就業規則の規定
就業規則には「始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨の規定が必要です。
就業規則を作成する義務のない常時労働者が10人未満の事業場では就業規則に準ずるものに定めることとなります。
第◎条 始業及び終業の時刻は、次の時間帯の範囲内で対象労働者の自主的な決定に委ねるものとする。
午前6時30分から午後10時まで
などと規定します。
労使協定の締結
次の❶から❼について、書面で労使協定を締結しなければなりません。
清算期間が1か月以内なら労使協定を行政に届け出る必要はありません。
❶適用対象の労働者の範囲
❷清算期間
❸清算期間における総労働時間
(以上が法律事項)
❹標準となる一日の労働時間
❺コアタイムを設ける場合にはその時間帯の開始及び終了時刻
❻フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその時間帯の開始及び終了時刻
❼清算期間が1か月を超えるとき、労使協定の有効期間の定め(労働協約除く)
(以上が省令事項)
労使協定で定める事項の詳細について
労使協定に規定する各事項の詳細については次のとおりです。
適用対象の労働者の範囲
「本社社員に限定する」とか、「▲部を除く全従業員」、「管理監督者及び裁量労働制適用者など特別の勤務制度が適用される者を除く」など、制度の適用者の範囲を規定します。
清算期間
その期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間である週40時間(特例措置対象事業場については清算期間が1か月以内なら週44時間)以内で労働させる期間のことで、3か月以内の期間を定めます。
第◎条 労働時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1か月とする。
などと期間の始点と終点が明確となるように規定します。
清算期間における総労働時間
清算期間内の所定労働時間の総数のことで、「総労働時間」といい、清算期間内の法定労働時間(週平均40(44)時間以内)内とする必要がありますので、その範囲は次の計算式で得られる時間数とします。
つまり
清算期間の総労働時間 ≦(清算期間の暦日数÷7日)×一週間の法定労働時間
❶暦日数が1か月の場合の法定労働時間の総枠
31日(177.1時間)
30日(171.4時間)
29日(165.7時間)
28日(160.0時間)
❷暦日数が3か月の場合の法定労働時間の総枠
92日(525.7時間)
91日(520.0時間)
90日(514.2時間)
89日(508.5時間)
具体的には、
第◎条 1か月の総労働時間数(所定総労働時間)は、就業規則第▲条の休日を除く暦日数に7.5時間を乗じた時間とする。
や
第◎条 3か月の総労働時間数を、508時間(固定時間)とする。
などと規定します。
清算期間が1か月を超える場合の要件
清算期間が1か月を超えるときは、さらに要件が加わることに注意が必要です。
清算期間が1か月超え(~3か月まで)の制度を導入する場合には、清算期間を通じて1週平均40時間以内とするほか、
❷1週当たり44時間が適用される特例措置対象事業場も1週当たり40時間の適用となる。
❸労使で締結した労使協定を添付して労使協定届を労基署長に届け出なければならない。
以上の要件が加わることに留意しましょう。
この記事は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入した場合に、時間外・休日労働がどのように適用されるのか改めて確認したい人や、違法な残業・休日労働とならないための注意点などについて知りたい人向けの記事です。フレックスタイム[…]
標準となる一日の労働時間
年次有給休暇を取得したときに労働したとみなされる1日の労働時間数のことを「標準となる一日の労働時間」とし、これを明確化します。
第◎条 一日の標準労働時間は7時間30分とし、年次有給休暇については7.5時間の労働とみなし取扱う。
などと規定します。
コアタイムを設ける場合
必ず勤務しなければならないコアタイムを規定することもできますが、その場合には開始時刻と終了時刻を規定します。
もちろん、コアタイムを決めないこともできます。
第◎条 社員が労働しなければならない時間帯は、10時から14時までとする。
などと規定します。
一斉休憩が求められる事業場では、このコアタイム時間帯に休憩時間を設定することが考えられます。
フレキシブルタイムに制限を設ける場合
始業時刻と終業時刻を労働者に任せる制度ですが、このフレキシブルタイムに一定の幅を設けることもできます。
第◎条 社員がその選択により労働することができる始業時刻帯は6時から10時30分まで、終業時刻帯は13時30分から22時までとする。
などと規定します。
労働時間の過不足の繰越
清算期間における総労働時間(所定労働時間総数)と実際に勤務した実労働時間とに乖離(過不足)がある場合には、次のような清算を行うことができます。
実労働時間に過剰があった場合
清算期間内の労働の対価はその期間の賃金支払日に支払われる必要がありますので、過剰労働分を次の清算期間中の労働時間の一部に充当はできないことに注意です。
つまり、当清算期間内で総労働時間を超えて労働した場合には、所定外労働として賃金を加算する必要があります。
法定時間内であれば、100分の100の賃金、法定外の時間外労働であれば100分の125以上の賃金を支給することになります。
実労働時間に不足があった場合
定められた総労働時間(所定労働時間総数)分の賃金をその期間の賃金支払日に支払いますが、不足時間分を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、
「法定労働時間の総枠の範囲内である限り、賃金の過払い清算と考えられ、基準法24条(賃金の全額払い)に違反するものではないこと」(昭和63.1.1 基発1号)と解されています。
したがって、たとえば完全週休二日制で一日の標準となる労働時間数を7.5時間として制度設計すると、1週当たり37.5時間の総労働時間になりますので、
=2.5時間×(清算期間内の暦日数÷7)
つまり、この場合ですと、ひと月当たりで10~11時間程度を”隙間時間”として、その範囲内の繰越清算ができるということです。
遅刻・早退・欠勤の扱い
1⃣ フレックスタイム制においては、始業及び終業時刻を労働者に委ねるという特性から、遅刻・早退の概念はないと言えます。
が、コアタイムを設けた場合には、その時間帯に出勤しない、遅刻・早退することに対する何らかのペナルティがなければ、コアタイム設定の意味が薄まります。
そこで、コアタイムに遅刻・早退・欠勤をした場合には、減給等何らかの処分対象とするとか、賞与等の査定に反映させるとかが考えられます。
2⃣ フレックスタイム制は労働の開始と終了の時刻について柔軟性を規定しているのみで、労働契約上勤務しなければならない労働日が設定されている以上、コアタイムが設定されておらず実質的に出勤日を労働者の自由に委ねる場合や、年休等正当な権利の行使による不就労以外は、所定労働日に労働しないことは欠勤に該当するものとして、欠勤に関する社内ルールを適用させることはできると考えられます。
3⃣ コアタイムの前後に出勤していたものの、肝心のコアタイムには就労していなかった場合などにはどういうペナルティを課すかについては、社内で整理検討すべきです。
4⃣ 遅刻・早退・欠勤があったとしても、清算期間における実労働時間の総数が総労働時間(所定労働時間総数)を下回っていない限り、所定の労働時間に対する決められた賃金は支給する必要があることに注意する必要があります。
フレックスタイム制適用の労働者の休日労働
1⃣ 「コアタイムを設けずに、実質的に出勤日を労働者の自由に委ねることとする場合にも、法定休日が確保されるようにするため、所定休日は明確に定めておく必要がある」(労働法コンメンタール「労働基準法(上)労働省労働基準局編)とされています。
このように、フレックスタイム制は休日についての規定(法定休日)を除外していませんので、コアタイムの設定されていないフレックスタイム労働者が出勤を自由に選定した結果生じる非労働日とそれ以外の法定外休日、法定休日との違いを理解して労務管理すべきでしょう。
2⃣ 特に、法定休日に勤務した場合(休日労働)には35%以上の割増賃金の支給が求められますので、総実労働時間数とは切り離して、休日労働の時間数を把握する必要があります。
時間外労働の上限規制(時間外労働と休日労働を合わせた時間数は、月100時間未満、月平均80時間以下)をクリアしているか否かを判断する際には、所定休日における勤務も含めた時間外労働のほか、法定休日の労働時間も合わせて算定する必要があることに留意する必要があります。
まとめ
フレックスタイム制は始業時刻と終業時刻が柔軟な労働時間制度ですので、勤務間インターバル制度を導入することとも親和性がある制度と考えますので、今後さらに導入企業は増えるのではないかと思います。
時間外労働の算定が日々行われるものではなく、清算期間を通じてまとめて算出されますので、日々や各週ごとの勤務では時間外労働が確定しないことから、時間外労働の管理には十分な注意が必要です。