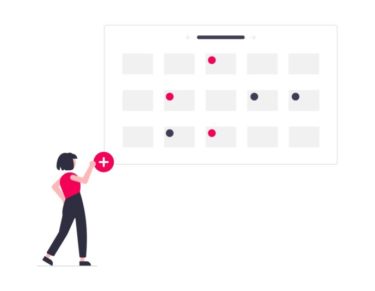日本企業の海外支店や支社で勤務する労働者については、どちらの国の労働法が適用されるのか迷ったことはありませんか?
日本国内にある外国企業に勤める労働者は日本の労働法の保護対象とはならないのでしょうか?
❷ 「法の適用に関する通則法」により、当事者が選択した国の法律を適用することができるが、労働契約に関し労働者が労務提供地の特定の強行法の適用を求めた場合それも適用されること
❹ 日本国内にある事業場は外国法人であっても日本法の強行法規が適用されること
労基法の罰則、行政指導は国外の事業場には及ばないが日本国内の使用者が処罰され得る
日本の会社から海外に異動して労働したところ、現地で労基法に抵触する事態が生じたときに、法の適用に関しては、労基法の「公法的側面」と「私法的側面」の両面の性質を踏まえて整理する必要があります。
労基法の罰則適用については、次のような行政通達があります。
労基法は、行政取締法規としては日本国内にある事業場にのみ適用されます(属地主義)。
したがって、商社、銀行等の支店、出張所等であって事業としての実態を備える海外の事業場については、労基法の適用はないこととなります。
ただし、現地で労基法違反の行為が行われた場合には、刑法総論の定めにより行為者に罰則を適用することはできませんが、日本国内にいる使用者に当該違反行為の責任があるときに限り、その使用者が処罰されることとなるわけです。
一方、例えば日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合において、一切の工事が日本にある業者の責任において行われており、国外における作業場が独立した事業としての実態がないと認められる場合には、現地における作業も含めて当該事業に労基法の適用があると解されます【同上通達】。
海外勤務でも労基法に基づく私法上の権利義務関係があることも
「改定」新版労働基準法(下)労働省労働基準局編 労働法コンメンタール(平成12年3月1日改訂新版)1013頁では、次のように解説しています。
労基法の民事的効力については、労基法が適用されない事業であっても、契約当事者が日本国の法によると定めた場合及び契約当事者の意思が明らかでなく契約地が日本国である場合には及ぶものと解して良いであろう【法の適用に関する通則法第8条参照】。
したがって、現地における労基法違反の行為について罰則が適用されることはないとしても、労働者は当該違反行為の行為者である使用者の民事上の責任を追及することができる場合があるであろう。
私法上の権利義務関係、つまり民事法規として日本の法律をベース(準拠法)にすることの選択があった場合などには、日本の法規の一つである労基法が当事者に適用されますので、労基法による罰則は追及されないものの、海外で勤務していても労基法に基づく権利義務の関係に立つことができるのです。
労働契約についてはどの国の法律をベースにするか(準拠法)について特別の扱いが認められている
どちらの国の法律を準拠法にするかの決め方は「法の適用に関する通則法」に規定されています。
原則は当事者が選択する
通則法第7条では、当事者による準拠法の選択を認めており、労働契約についてもその適用があります。
当事者の選択がなければ最も密接な関係がある地の法による
当事者による選択がない場合、通則法第8条では、当該法律行為の当時において法律行為に最も密接な関係がある地の法によるとしています。
ここで、 通則法第12条3項では、労働契約に関しては、最密接関連地は労務提供地と推定するとしています。
ただし、明示の選択がないから直ちに労務提供地の法が準拠法になることが確定するかというと、そうでもなく、実際上は種々の事情を踏まえて黙示の選択が認定され得ることに注意です。
外国法人と雇用契約を交わした日本国籍の労働者が、明確に準拠法を選択していなかったところ、外国会社と訴訟に至りましたが、準拠法は会社の本社がある外国の法である旨の判断をされた事例があります。
ドイツの航空会社に雇用された日本国籍の客室乗務員が、ドイツにおける税制改正に伴い、手当支給が廃止されたことに対し、支払い請求訴訟を提起したもの。
▷ 裁判所は、
・雇用契約上労働者の権利関係はドイツの本社と労働組合による労働協約に基づいており、これはドイツ労働法等の規範に基づいている
・労働条件の交渉もドイツの本社と本社の従業員代表を通じてなされており、労働者も個別の労働条件について本社と交渉してきた
・労務管理や指揮命令、フライト日程作成などは、ドイツの担当部門で行われ、
・給与はドイツマルクで支給されていた ・採用面接は日本で行われたが、本社人事部が来日し行い、雇用契約は本社担当者との間で締結されていた
等を総合判断すれば、雇用契約の準拠法はドイツ法であるとの黙示の合意が成立していたものと推定することができる。
休養、休日等の取得場所として日本にホームベースがあったことのみでは、雇用契約の準拠法を日本法とする合意が成立していたと推認するには足りない
として準拠法を日本法と推定することを認めなかったのです。
準拠法の選択に関係なく労務を提供している地の法の強行規定を適用することができる
特例として、労務提供地以外の地の法が準拠法として選択されている場合であっても、労働者が労務提供地の特定の強行規定を適用すべきことを求めたときは、その強行規定が適用されるのです。
例えば、ある国では「未消化の有給休暇について1日につき賃金の3倍」の手当を支給することが強行規定であったならば、その国の事業場に勤務する労働者がそれを請求してきたなら支払わなければならないことになるのでしょうね。
日本国内にある事業場は原則として労基法等の強行規定が適用される
労基法、最低賃金法、労働安全衛生法など刑事制裁や行政取締により実効性を確保する強行的な労働保護法規は日本国内において営まれる事業に対しては、当事者の意思の如何を問わず、適用されると解されています。
通則法の労働者保護の観点から、最密接関係地法を準拠法に選択しなかった場合も、労働者の意思表示により同地の特定の強行法規が適用されます。
海外出張と海外派遣の違い
海外で勤務すると言っても、それが「出張」によるものか、「派遣」による異動なのかえは、その性格が違ってきます。
「海外出張」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいいます。
「海外派遣」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務することです。
こうした違いは、次の表のように厚労省の「特別加入制度のしおり」に掲載されています。

● 海外出張の場合は、国内事業主の指揮命令により海外で用務を遂行し、その期間中は国内事業主の指揮命令を包括的に受け、海外の就労場所が独立した一の事業として認められる余地がないことから、海外の就労場所も含めて日本国内の一の事業として労基法等の適用があると解されます。
● 海外派遣の場合は、就労場所が独立した一の事業所であるときは、労基法の罰則規定は適用されませんが、違法な状況が生じ、日本国内にある使用者にその責任がある場合には、この使用者は処罰対象となるのです。
まとめ
日本から見て、海外の事業場に一時的に出張したり、海外の事業の一切が日本国内の会社の責任下に置かれ、海外事業場の独立性が認められないような場合は、海外事業場も含め日本国の会社に労基法が全面的に適用あるといえるでしょう。
一方で、海外の事業場に異動により派遣された場合で、当該事業場が独立しているときは、海外事業場に対しては労基法の行政取締規定や刑事罰の適用はありません。
ただ、日本国内の使用者に違反行為があると認められるならその限りでその使用者が処罰対象になり得るということです。
公法的な法の適用とは別に、私的な関係を見た場合、労使の当事者がどのような契約を交わすか、あるいは状況によっては「黙示の選択の認定」により、どちらの国の法による雇用契約関係にあるといえるのか、結論が違ってきます。
なお、刑事罰をもって強制される「強行法規」の適用については、勤務している国のそれらについて重大な関心をもたざるをえないということが言えます。