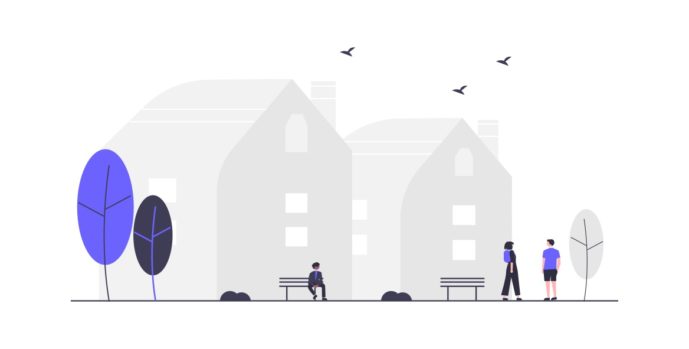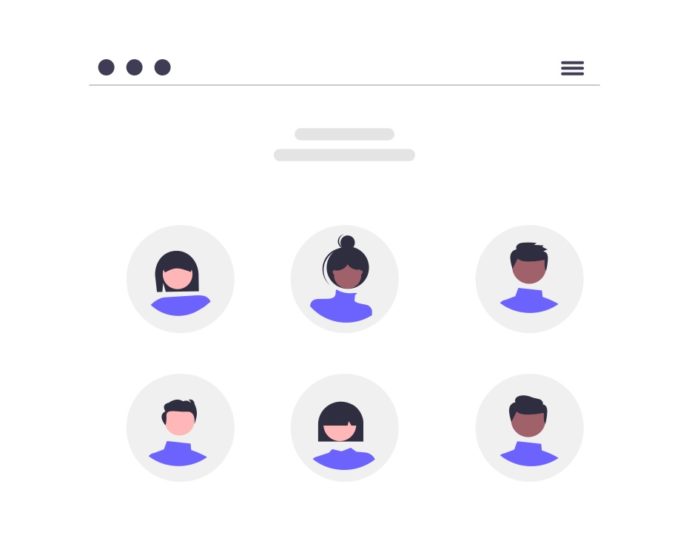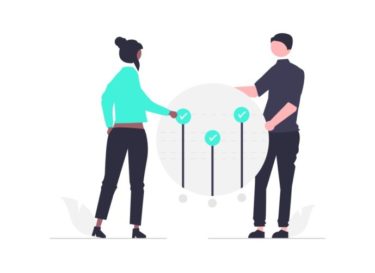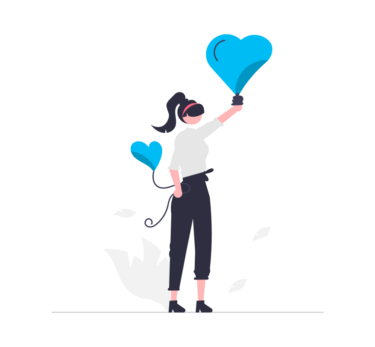本業のほか兼業や副業など複数の事業場で就労する労働者(複数事業労働者)の負傷、疾病、障害、死亡に関しては、以前までは労災が発生した一つの事業場の賃金額だけをベースに労災補償の給付額が算定されていました。
しかし、労災保険法の改正により、2020年9月以降に発生した労災からは、複数事業労働者が被災したときには、災害が発生していない他の就労事業場の賃金額も含めて、労災補償の給付額を決めることとされました。
さらに、労災認定に関して、個別の事業場ごとの状況では労災認定ができない場合でも、就労していた複数の事業場を通じて労働時間などのストレスを総合的に評価・判断して労災認定を行う新たな制度が創設されました(複数業務要因災害)。
この改正により、労働者や労働者には当たらない特別加入者にとってどんな影響があるのか、関係する複数の会社は皆、補償責任を分担することになるのか、など制度改正で何が変わったのか整理しました。
❷発症時点で複数事業に就労していなくても、発症の原因・要因が生じた時点で複数事業に就労していた者も複数事業労働者扱いとなる
❸複数事業労働者の業務災害・通勤災害時には災害発生のない就労先の賃金額も合算して保険給付額が決まる
❹複数事業労働者の業務災害が発生していない使用者についてはこれまでと同様、労基法上の補償責任はない
❺複数業務要因災害ではどの使用者にも労基法上の補償責任がない
❻被災した複数事業労働者はどれか一つの事業を管轄する労基署に労災請求する
❼被災した複数事業労働者は複数事業に就労していることを明記して労災請求する
複数事業労働者の対象となる労働者を確認
労災保険法上の「複数事業労働者」は「事業主が同一でない2以上の事業に使用される労働者」と定義されています(労災保険法1条)。
これには、次の①から③の者も該当します。
①傷病等の原因や要因となる事由が生じた時点で同時に複数事業主と労働契約関係にあった労働者
傷病などが発生した時点ではすでに複数の事業場では就労していない場合でも、複数事業労働者に該当し得るというのがミソです。
「傷病等の発生」はその原因・要因が形成されてから時間経過後に認められる場合がありますし、労災認定上大事なのはその「原因・要因となる事由が生じた」ことですので、そのときに複数の事業で就労していた者が該当する、としています(法7条1項2号、労災則5条)。
②労働者であって、他の事業場において特別加入している者
ある会社とは雇用関係にあると同時に、他の就業については特別加入している場合も該当します。
③複数の事業において特別加入している者
特別加入は労働者に準じて労災保険の加入を認めるのにふさわしい者としている観点から、複数事業労働者に含めて保護の対象とされています。
複数事業労働者が一つの事業で労災にあったとき
これまでの不都合
複数の事業で就労している者が、仮に仕事で負傷等して休業する場合、負傷等した会社で支給されていた賃金が支給されないことによる補填(休業補償給付)を、その会社の賃金額だけを基に算定されて給付されていました。
負傷等の発生とは関係のない会社も同時に休業することで、こちらの会社からの賃金も受けることができなくなることもあります。
しかし、労災が発生した会社ではないため、業務災害に対する補償責任がないことから、この会社の賃金不支給については労災保険の休業補償給付などの対象にはなりませんでした。
二つの事業に就労していて急逝した労働者の遺族が、両社の労働の相乗効果で発症したのだから両社に業務起因性を認め、賃金も合算して遺族補償給付等をすべき、と訴えた事件において、裁判所は次のとおり判断しました。
遺族補償給付をどのように定めるかは立法府の合理的な裁量に委ねられているというべきであり、二重就労者が一の事業場の業務に起因して負傷、疾病障害又は死亡に至った場合に労災保険法の趣旨や遺族補償給付の性質を根拠として直ちに平均賃金の算定において複数事業場の賃金を合算することが当然に帰結されるものではない・・・両事業場での就労を併せて評価して業務起因性を認めて労災保険給付を行うことは、労基法に規定する災害補償の事由が生じた場合に保険給付を行うと定めた労災保険法12条の8の明文の規定に反するというほかない。
被災者にとっては、複数の事業における就労で得ていた収入が無くなるわけですので、賃金補償が一部に限定されていると収入減への補償としては十分ではありませんでした。
以上が、2020年9月前までの労災保険制度であったわけです。
改正後の状況
こうした複数事業労働者に対する「稼得能力の補填」の観点から、制度改正後は、関係する複数事業における賃金額を合算した額を基礎に算定された給付を行うこととされ、実際上の収入減全体に対する補填となりました。
労災発生と無関係な会社にとっては、自社の安全配慮が及ばないところで突然労災により休業などされることで、迷惑を被ったとの感を抱くことでしょう。
ただ、被災者に対する労災補償が実際の損失に対応した内容になることから、被災者が安心して療養等し早期の回復による早期の職場復帰を期待できるといった労働者保護が図られることで、関係するすべての会社にとって雇用安定にもつながる効果を期待できる面もあると言えそうです。
この場合、業務災害を発生させていない事業場においては労災保険料の負担上の不利益は生じません。
複数事業での業務を原因とする労災保険給付の創設
以前までは、就労する複数の事業ごとに業務上の負荷などを評価し、それぞれの事業ごとでは業務災害とは認められない場合、仮に複数事業全体を一つの事業としてみれば業務災害に認定可能な場合でも労災保険の給付は行われませんでした。
制度改正により、各事業における業務上の負荷等を総合的に評価すれば、当該業務と傷病等との間に因果関係が認められる場合には、複数の事業の業務を総合的に要因とする「複数業務要因災害」を新たに労災保険給付の支給事由の一つとしたのです(法7条1項2号)。
複数業務要因災害は「業務災害」とは違う
複数の就労先での業務上の負荷を総合することで初めて疾病等との因果関係が認められる複数業務要因災害は、単一の事業で認められる業務災害とは全く別物であることを理解しなければなりません。
複数業務要因災害は、個々の就労先ごとでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない労災を指すので、個々の就労先は労基法上の災害補償責任(労基法第8章の災害補償)を負わないとされます(2019年12月23日労働政策審議会建議、2020年8月21日付け基発0821第1号)。
労基法は、基本的に、使用者とは別の他の使用者における就労を合わせた措置義務などを規定していません(労働時間の通算規定は複数使用者を通じた扱いも含むとされていますが)。
一つの使用者の下で業務上負傷等した業務災害に認められないのなら、その使用者については労基法上の災害補償責任の規定は適用されません。
そうなると、
複数業務要因災害の対象となる労災は限定的
複数事業の業務全体で総合的に評価して労災認定判断をする負傷等は、
①従事する2以上の事業の業務を要因として負傷した場合
②従事する2以上の事業の業務を要因として疾病にかかった場合
が対象となりますが(労災保険法20条の3第1項)、
対象疾病については規則で「脳・心臓疾患」と「精神疾患」及び「その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病」
と規定されており、その範囲は限定的です。
事実上、過労死や過労自殺、精神疾患関連の労災に関して、複数の就労先の負荷も加味して労災認定をするために、複数業務要因災害という新しい補償対象を創設したといったところです。
複数事業労働者はどこの労基署に労災保険の請求をするのか
複数事業労働者が一般の業務災害や複数業務要因災害に関する労災保険の申請を行うときは、就労している複数の事業場が他県他市も含め分散していることもあり、どちらの労基署に申請していいのか迷うかと思います。
一般の業務災害や通勤災害に関しては、これまでどおり、災害が発生した事業場を管轄する労基署に労災請求の申請書を提出します。
複数の事業場で就労している場合は、各事業場を管轄する労基署のどちらにでも申請書を提出してよいことになっています。
就労している(していた)複数の事業場を管轄するそれぞれの労基署に提出する必要はありません。
複数事業労働者であることを明確に
申請に使用する様式は、一般の業務災害と複数業務要因災害とで同じ様式を用います。
そこで、新たに追加された「その他就業先の有無」欄に何も記載しない場合には「複数事業労働者」とみなされず、一般の業務災害のみの申請と扱われます。
「その他就業先の有無」欄に記載してある申請については、業務災害と複数業務要因災害に関する保険給付を両方請求したものとして労災認定の判断を行うこととされています(2020年8月21日付け基発0821第1号)。
行政の体制
行政の体制上の話しですが、法律上は、複数業務要因災害に関する事務を所管するのは、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所(一般には賃金総額の最も高い事業場でしょう)を管轄する労働局又は労基署となっています(規則1条)。
そして、一般の業務災害に関する事務を所管する労働局・労基署で保険給付に関する調査を優先して行うことから、複数業務要因災害に関する事務を所管する労働局・労基署は事務の一部または全部をその業務災害の調査を行う局・署に委嘱できることとなっています(規則2条の2)。
そいういった建付けにより、実務的には、これまで同様、一般の業務災害の労災認定判断を行う局・署がそのまま関連する複数業務要因災害に関する処理も担うのが主となるのではないかと推察されます。
なお、複数事業労働者がA社からB社に移動する際に途中で災害(交通事故など)で負傷等した場合には、移動の終点事業場(B社)において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、移動の間に起こった災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場(B社)の保険関係で行うものとされています(平成18年3月31日付け基発0331042号)。
まとめ
2020年9月1日以降に実際に疾病にかかったとか負傷した場合に、新たな複数事業労働者、複数業務要因災害が適用されることになっています。
疾病等の「原因や要因が生じたのが」2020年9月1日以前であっても、実際の負傷等が2020年9月1日以降に生じれば、この新たな労災保険制度の対象となり、負傷等の発生がそれ以前であれば、従来の建付けで処理されますので注意が必要です。